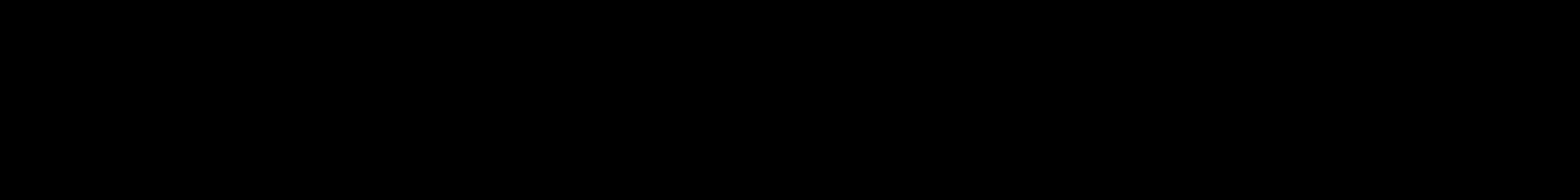前回の記事では、「しなり」が打撃に与えるメリットやその理論的な背景について解説しました。今回はさらに一歩踏み込み、しなりの感覚を実際に身につけるための具体的なトレーニング方法をご紹介します。
初心者でも始めやすく、学生から社会人まで幅広く活用できる練習法を段階的にまとめました。
しなりトレーニングの基本方針|感覚をつかむ・筋力をつける・実戦で試す

しなりを活かすためには、下半身から上半身へのスムーズな連動と、バットの弾性を感じ取る感覚が欠かせません。以下の3つが、しなりを習得するうえでの柱になります。
- 力みを減らす:余分な筋肉の緊張を抑え、必要な筋肉だけを適度に使う
- タイミングを掴む:バットがしなる→戻るサイクルをインパクトと一致させる
- 段階的に負荷を上げる:軽いバット→標準→重いバットの順に進めることでフォーム崩れを防ぐ
しなり特化型バットの活用も有効|「GoodManリベイター」の特徴と活用法
しなりを効率よく習得するには、専用設計のバットを使うのが効果的です。中でもGoodManリベイターは、細くしなやかな構造により、スイング時のたわみや戻りを実感しやすい設計が特長。無理な力を抜くフォーム作りにも役立ちます。
初心者でも扱いやすく、軽量バットの次のステップとして最適です。ティーバッティングや素振り練習と組み合わせると、しなりのタイミングや連動を自然に身につけられます。慣れてきたら通常バットとの併用で、実戦感覚へとつなげていきましょう。
ステップ1|軽量バットでの素振り

しなりを習得する最初のステップは、軽くて扱いやすいバットを使って、バットの「たわみ」と「戻り」を体で感じ取る練習です。重いバットでは体幹の使い方より腕力に頼りがちになるため、フォームやリズムを整える意味でも、まずは軽量バットからスタートしましょう。
練習方法|ゆったりとしたスイングで“しなりの流れ”を体感する
- ジュニア用や軽量トレーニングバットを使用する
- スイングは速さを求めず、ゆっくりと振るのがポイント
- バットがしなる→戻るタイミングを意識して、インパクトの位置と一致させる感覚を養う
- 1セット10〜15回を2〜3セット、鏡の前や動画でフォームを確認しながら行うと効果的
この段階では、飛距離や打球速度は意識しなくて大丈夫です。フォームの再現性や、しなりの「リズム」を掴むことに集中しましょう。
注意点
- 腕に力が入りすぎないように注意:肩や腕で振るとバットがしならず、ただの“振り回し”になります
- 下半身を主導に使う意識を持つ:膝・腰の動きと連動させて、体幹からバットへと力を伝える
- 無理に速く振ろうとしない:速さよりも「たわみ→戻り→インパクト」の感覚を丁寧に確認する
- フォームのブレを防ぐ:毎回同じ軌道を意識しながらスイングすることで、しなりが安定して発生するようになる
このステップで大切なのは、力を抜くことと体をうまく使うことです。バットの動きに自分の体が自然に連動する感覚を養うことで、次の段階のトレーニングが格段にスムーズになります。
また、自分の体格に合った長さ・グリップの太さのバットを選ぶと、フォームが安定しやすくなります。バッティングセンターなどで試し振りができる場所を活用しましょう。
ステップ2|中量~重いバットで筋力強化&しなり維持

軽量バットでしなりの感覚を掴んだら、今度は標準重量のバット、さらにはやや重いバットへと切り替えます。このフェーズで目的となるのは、しなりをキープしつつ、筋力アップを狙うことです。
重いバットは、扱いにくさと引き換えに「下半身主導でスイングする意識」や「体幹の使い方」を鍛えるのに効果的です。無理に力で振ろうとせず、しなりを活かす動作を維持できるかどうかが大切になります。
練習方法|段階的な重量アップでしなりを維持しながら筋力強化
- 標準バット→やや重めのバットへと、段階的に切り替えていく
- 1セット8〜10回を2セット程度を目安にスイングを実施
- バットの重さに負けないよう、下半身と体幹を軸とした動きでスイングする意識を持つ
- 可能であれば、軽量→標準→重めの3本をローテーションし、感覚と筋力の両面を鍛える
この練習を通じて、単なる筋力アップではなく、「フォームを維持しながら力を伝える」技術を習得していきます。
フォーム崩れを防ぐチェックリスト
この段階では、「振るための力」ではなく「しなりを維持するための力」を身につけることが重要です。フォームの安定と下半身主導の動きを軸に、重さに負けない“効率的なスイング”を習得しましょう。
- 腕力に頼らない:重いバットでも、腕で振ろうとするとフォームが崩れ、しなりも失われます
- 上半身の前傾を防ぐ:重さに引きずられて、姿勢が崩れていないか常に意識する
- 手首の硬直に注意:バットを支える手首に無理な力が入っていないかをチェック
- 膝の流れを防ぐ:インパクト時に膝が前に突っ込んでいないかを確認し、体重移動を丁寧に行う
ステップ3|チューブトレーニング&上半身・体幹強化

チューブトレーニングは、しなりを支える筋肉(特に肩周り・背筋・腹斜筋など)をピンポイントで強化するのに有効です。実際のバットを振るときに近い動作を再現しつつ、負荷の調整が簡単なため、初心者でも安全かつ効率的に取り組めます。
練習方法|スイング動作+回旋運動で「支える筋肉」を刺激する
- チューブ素振り
バットの代わりにチューブを握り、スイング動作を再現。チューブの抵抗を利用して、しなりに関与する筋肉の連動を高める。 - ツイスト運動(体幹の回旋強化)
足を肩幅に開いて立ち、チューブを使いながら上半身を左右にひねる動作を繰り返す。スイング時の“回転力”を強化できる。
各メニュー10~15回×2~3セットを目安に行うのがおすすめです。週2~3回の頻度で継続すると、筋力と動作の安定感が向上します。
注意点
- 力で引っ張りすぎない:無理に引っ張ると、動作が硬くなり逆効果。あくまで「しなやかな動き」を意識する
- チューブの強度は段階的に:最初から強い負荷をかけるのではなく、自分の筋力や目的に応じて調整する
- 反動を使わずにゆっくり動かす:反動に頼らず、筋肉を使って動かすことを意識するとより効果的
- 腰や背中を反りすぎない:姿勢が崩れると体幹に効かないため、フォームは常に鏡などでチェックする
チューブトレーニングは、見えにくい「支える筋肉」を鍛える手段として非常に優秀です。地味なようでいて、しなりの再現性やブレのないスイングにつながっていきます。
実戦スイングで最終調整――ティーバッティング&マシン打撃
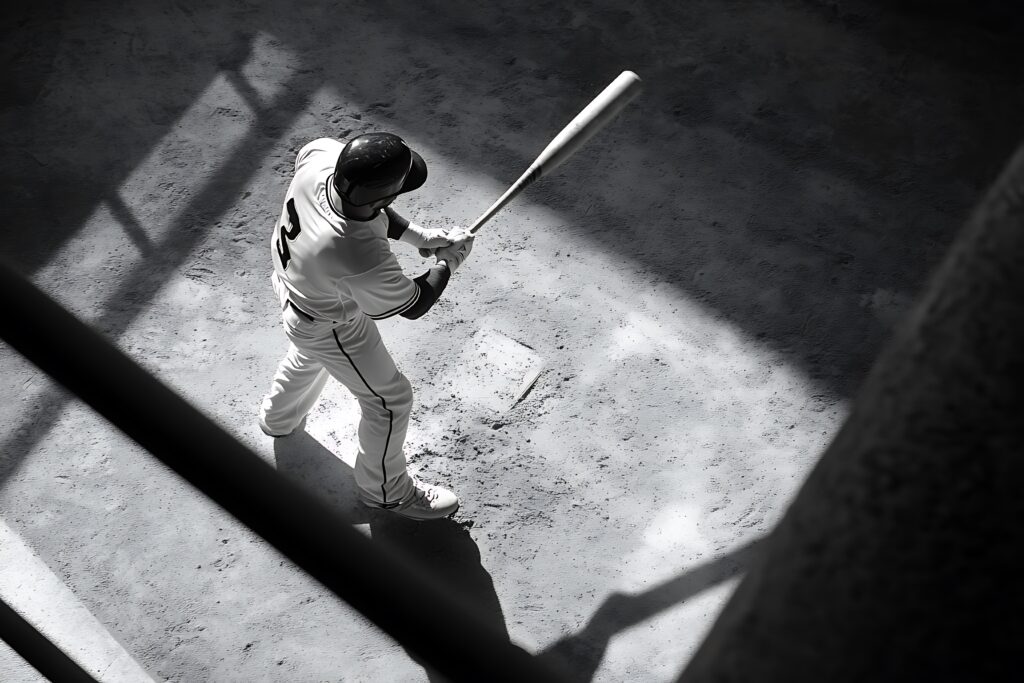
軽量・重量バットでの素振りと、体幹トレーニングで感覚と筋力を整えたら、いよいよ実戦形式でのスイングへと移行します。このステップでは、実際の打球を通じて「しなりの効果」が出ているかを確認しながら、インパクト精度とタイミングを磨きます。
練習方法|静止球と速球を使い分けてスイング精度を高める
- ティーバッティング
静止したボールを使い、「バットのしなり→戻り→インパクト」が一致しているかをじっくり確認。フォームの確認に最適。 - マシン打撃
ある程度スピードのある球に対しても、しなりを活かしたスイングが維持できているかをチェック。反応速度とフォームの安定性を磨く。
軽量→標準→重量バットを1打席ごとに交互に使う練習で、感覚とパワーのバランスを調整。スイングの再現性が高まります。
注意点
しなりを実戦で活かすには、どんな状況でもフォームが安定し、タイミングが取れているかがカギになります。ここまでのトレーニングの成果を、確かめながら仕上げていきましょう。
- ボールに当てることを目的にしない:とにかく当てようとするスイングでは、しなりが発揮されない
- インパクトのタイミングに集中:バットが戻る瞬間とインパクトを合わせる意識を常に持つ
- フォームの崩れに気づけるよう動画を活用:お互いのスイングを撮影・比較しながら学ぶと理解が深まる
- 疲労時こそ丁寧に:疲れてくると体幹が使えなくなり、しなりが失われやすくなるため、集中力を保つこと
「しなり」を活かすトレーニングを習慣化して打撃力UP!
しなりを身につけるためのトレーニングは、段階的な負荷調整とフォームチェックが鍵です。軽量バットで感覚を掴み、重いバットやチューブトレーニングで筋力と連動を高め、最後に実戦スイングで確かめる。このステップを継続すれば、確実にしなりの威力を感じ取れるはずです。
次回記事では、このトレーニングを実践して結果を出した野球打者たちの具体的な成功事例を紹介します。「本当に効果があるの?」と感じている方も、リアルな体験談からヒントを得られるかもしれません。