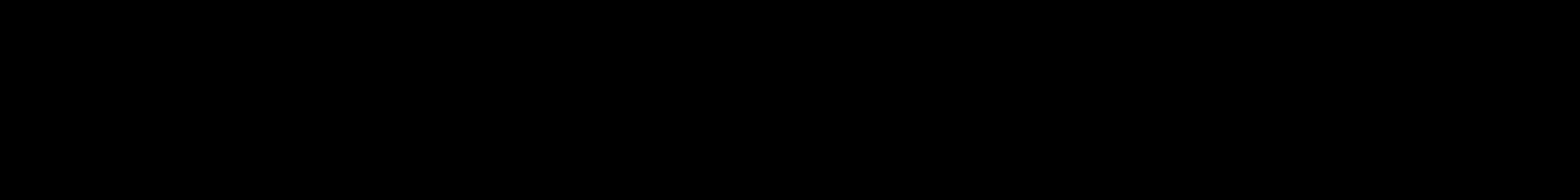四球と死球の違いとは?ルールや記録上の扱いをわかりやすく解説します。さらに、実際の試合で見られる印象的なシーンや選手の反応も紹介。本記事を読めば、「外れる球」と「当たる球」の違いが打率や打点にどう影響するのかが理解でき、野球観戦がより面白くなります。
四球と死球の基本的な違いを解説

野球観戦を始めたばかりの方が混同しやすい「四球(しきゅう)」と「死球(しきゅう)」。
ピッチャーのコントロールが定まらず、ボール球を4つ投げてしまうのが「四球」、ピッチャーの投げたボールがバッターに当たってしまうのが「死球」です。
両者の違いを分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 四球(フォアボール) | 死球(デッドボール) |
|---|---|---|
| 発生条件 | 1人の打者に対してボールが4つ宣告される | 投球が打者の身体(ユニフォーム含む)に当たる |
| 主な原因 | 投手の制球難 | 投手の失投や戦術的な投球 |
| 英語表記 | Base on Balls (BB) | Hit by Pitch (HBP) |
どちらもピッチャーの投球によってバッターがアウトになることなく一塁へ進むことができるプレーですが、内容は全く異なります。まずは、2つの基本的な違いをしっかりと理解しましょう。
四球(フォアボール)とは投球がボールになること
四球とは、ピッチャーが投げたボールがストライクゾーンを外れ、「ボール」と判定される投球が同一打者に対して4回宣告されることです。一般的には「フォアボール」という名称で広く知られています。
野球のルールでは、ストライクを3つ取られるとバッターは三振でアウトになりますが、逆にボールが4つになると、バッターはアウトにならずに一塁へ進む権利(安全進塁権)を得られます。
これは、ピッチャーのコントロールミスによるもので、バッターがヒットを打ったわけではありませんが、「出塁」という形で記録されます。
死球(デッドボール)とは投球が打者に当たること
死球とは、ピッチャーの投げたボールがバウンドせずに、バッターの身体や着ているユニフォームに当たることです。「デッドボール」という名称が一般的で、英語では「ヒット・バイ・ピッチ(Hit by Pitch)」と呼ばれます。
投球が打者に当たった場合、ボールカウントに関わらず、バッターは一塁へ進むことができます。ただし、バッターが意図的にボールに当たりにいったと審判が判断した場合や、ストライクゾーンを通過した投球に当たった場合などは、死球とはならずストライクが宣告されることもあります。
ピッチャーの失投によって起こることがほとんどですが、ときには内角を厳しく攻める戦術の結果として発生することもあるプレーです。

四球と死球の違いを比較解説【ルール編】

野球の試合で、打者がボールを打たずに一塁へ進むことができる「四球(フォアボール)」と「死球(デッドボール)」。
どちらも出塁という結果は同じですが、ルール上の発生条件やその後の展開には明確な違いがあります。ここでは、ルールに焦点を当てて、両者の違いを詳しく比較解説していきます。
ボールカウントにおける違い
四球と死球の最も基本的な違いは、その成立に関わるボールカウントです。ボールカウントとは、ストライクとボールの数を数えるもので、打席の結果を大きく左右します。
| 種類 | 成立条件 | ボールカウントとの関係 |
|---|---|---|
| 四球 | 1つの打席でボールが4回宣告される | ボールカウントが「4ボール」になることで成立 |
| 死球 | 投球が打者の身体やユニフォームに当たる | ボールカウントに関わらず成立 |
四球は、ピッチャーの投球がストライクゾーンを外れる「ボール」の判定を4回受けることで成立します。
つまり、ボールカウントが「4ボール」になった時点で、打者は四球を選んだことになります。これに対し、死球は、ボールカウントに関係なく、ピッチャーの投球が打者の身体(ユニフォームを含む)に当たった瞬間に成立します。
たとえ2ストライクと追い込まれている状況でも、投球が体に当たれば死球となります。
打者が一塁へ進める条件の違い
四球と死球はどちらも打者に一塁への安全進塁権が与えられますが、死球には特定の条件下で進塁が認められない例外ルールが存在します。
四球の場合、4つ目のボールが宣告された時点で、打者は無条件で一塁へ進むことができます。しかし、死球の場合は、以下のケースでは一塁へ進塁できず、判定が変わることがあります。
- 投球がストライクゾーンを通過していた場合:打者が避けようとしたかどうかにかかわらず、ストライクが宣告されます。
- 打者が投球を避けようとしなかったと審判が判断した場合:ストライクゾーンを外れていても、打者が意図的に当たりにいった、あるいは避ける動作を見せなかったと見なされると、死球とはならず「ボール」が宣告されます。
- 打者がスイング(打とうとする行為)をした場合:投球が体に当たっても、バットを振っていればストライクとなります。
このように、死球が認められるかどうかは、打者の動作や投球のコースといった要素を審判が総合的に判断して決定されます。一方、四球にはこのような例外的な条件はありません。
故意四球と危険球というルールの違い
四球と死球には、それぞれ特殊な状況で適用される「故意四球(敬遠)」と「危険球」という特別なルールが存在します。これらは戦略や選手の安全に関わる重要なルールです。
故意四球(敬遠)と申告敬遠
故意四球、通称「敬遠」とは、守備側が強打者との勝負を避けるなど、戦略的な理由で意図的に四球を与えることです。 かつてはピッチャーがボール球を4球投げる必要がありましたが、試合時間短縮などを目的に、2018年から「申告敬遠」というルールが導入されました。
これは、守備側の監督が審判に敬遠の意思を伝えるだけで、実際に投球することなく打者を一塁へ進塁させることができる制度です。 もちろん、従来通り4球投げて敬遠もできます。
危険球と退場処分
死球の中でも、特に悪質または危険と判断された投球には「危険球」というルールが適用されます。日本プロ野球(NPB)のルールでは、投球が打者の頭部に当たり、審判員がそれを危険球と判断した場合、ピッチャーは即座に退場処分となります。 これは選手の安全を確保するための非常に厳しい措置です。
ただし、すべての頭部への死球が危険球となるわけではなく、例えばすっぽ抜けた変化球のように、審判が危険ではないと判断した場合は警告に留まることもあります。
四球と死球の扱いの違いを解説【記録編】

四球(フォアボール)と死球(デッドボール)は、どちらも打者が一塁へ進むことができる点は共通していますが、記録上の扱いは異なります。選手の成績を評価する上で重要な「打数」「打率」「出塁率」「打点」にそれぞれどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
打数と打席のカウント方法の違い
まず、野球の記録における基本的な考え方として「打席」と「打数」の違いを理解することが重要です。四球と死球はどちらも打数にはカウントされませんが、打席にはカウントされます。
これは、打者が打つ意思を見せる前に一塁へ進むことが確定するため、打撃結果とは見なされないからです。
| 項目 | 四球(フォアボール) | 死球(デッドボール) |
|---|---|---|
| 打席 | カウントされる | カウントされる |
| 打数 | カウントされない | カウントされない |
「打席」は打者がバッターボックスに入り、アウトになるか出塁するかで打撃を完了した回数を指します。 一方、「打数」は打席数から四球、死球、犠打、犠飛などを除いたもので、打者の純粋な打撃能力を測るための指標です。
出塁率と打率への影響の違い
四球と死球は、打者の評価指標である「打率」と「出塁率」に異なる影響を与えます。
打率への影響
打率は「安打 ÷ 打数」で計算されます。 四球も死球も打数に含まれないため、四球や死球を選んでも打率が下がることはありません。 ヒットを打てなくても打率を維持したまま出塁できるため、チームへの貢献につながります。
出塁率への影響
出塁率は「(安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)」という計算式で算出されます。 この計算式からもわかるように、四球や死球は出塁率を上げる重要な要素です。 チームの得点機会をどれだけ作り出せるかを示す指標であり、近年その重要性が増しています。
| 項目 | 四球(フォアボール) | 死球(デッドボール) |
|---|---|---|
| 打率への影響 | 変動しない | 変動しない |
| 出塁率への影響 | 上昇する | 上昇する |

打点に関するルールの違い
打点とは、打者の打撃によって走者が得点した場合に記録されるものです。 四球と死球で打点が記録されるかどうかは、塁の状況によって決まります。
基本的には、四球や死球そのもので打点がつくことはありません。しかし、満塁(すべての塁に走者がいる状態)の場面で四球または死球が与えられた場合、打者には打点1が記録されます。
これは、三塁走者が押し出される形でホームインするためで、「押し出し」と呼ばれます。 満塁以外の場面では、四球や死球によって走者が進塁して得点しても、打者の打点にはなりません。
プロ野球における四球と死球の有名な記録

プロ野球の長い歴史の中では、四球や死球に関する数々の記録が生まれてきました。これらの記録は、単なる数字以上の意味を持ち、選手のプレースタイルや他球団からの警戒度、そして投手との熾烈な駆け引きを物語っています。
ここでは、後世に語り継がれるであろう、四球と死球の金字塔を打ち立てた選手たちを紹介します。
最多四球記録を持つ選手
四球の多さは、打者の優れた選球眼と、相手バッテリーから勝負を避けられるほどの脅威を兼ね備えていた証と言えます。特に、歴史に名を刻む強打者たちは、その圧倒的な長打力を警戒され、多くの四球を記録しています。
“世界の王”が持つ不滅の大記録【通算記録】
プロ野球における通算最多四球記録は、読売ジャイアンツなどで活躍した王貞治選手が持つ2390個です。 この記録はNPB(日本野球機構)だけでなく、世界記録でもあり、今後破られることは極めて困難とされるアンタッチャブルレコードの1つです。
王選手は通算868本塁打という世界記録も保持しており 、その長打力を恐れた相手チームから故意四球(敬遠)で勝負を避けられるケースが非常に多かったことが、この大記録につながりました。 通算の故意四球だけでも427個にのぼります。
| 順位 | 選手名 | 四球数 | 実働期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王 貞治 | 2390 | 1959-1980 |
| 2 | 落合 博満 | 1475 | 1979-1998 |
| 3 | 金本 知憲 | 1368 | 1992-2012 |
| 4 | 清原 和博 | 1346 | 1986-2008 |
| 5 | 張本 勲 | 1274 | 1959-1981 |
驚異的なペースで四球を選んだ王貞治【シーズン記録】
シーズン最多四球記録も王貞治選手が1974年に記録した158個です。 この年の王選手は三冠王を獲得しており、まさにキャリアの絶頂期にありました。
シーズン記録のランキング上位は王選手の名前で占められており、いかに他球団から恐れられていたかがうかがえます。
| 順位 | 選手名 | 所属球団 | 四球数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 貞治 | 読売ジャイアンツ | 158 | 1974年 |
| 2 | 王 貞治 | 読売ジャイアンツ | 142 | 1966年 |
| 3 | 王 貞治 | 読売ジャイアンツ | 138 | 1965年 |
| 4 | 王 貞治 | 読売ジャイアンツ | 130 | 1967年 |
| 4 | 丸 佳浩 | 広島東洋カープ | 130 | 2018年 |
最多死球記録を持つ選手
死球の多さは、投手に内角を厳しく攻められながらも、決して踏み込みを恐れない打者の闘志の現れと解釈できます。強打者の宿命ともいえるこの記録には、数々の名選手が名を連ねています。
“番長”の愛称で知られた強打者の勲章【通算記録】
通算最多死球記録は、西武ライオンズや読売ジャイアンツなどで活躍した清原和博選手の196個です。
清原選手は、その豪快なスイングとカリスマ性でファンを魅了しましたが、同時に相手バッテリーからの厳しい内角攻めに晒され続けました。
しかし、それに臆することなく打席に立ち続けた結果が、この不名誉ながらも彼の勇敢さを示す記録につながっています。
| 順位 | 選手名 | 死球数 | 実働期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清原 和博 | 196 | 1986-2008 |
| 2 | 竹之内 雅史 | 166 | 1968-1982 |
| 3 | 衣笠 祥雄 | 161 | 1965-1987 |
| 4 | 阿部 慎之助 | 152 | 2001-2019 |
| 5 | 村田 修一 | 150 | 2003-2017 |
体を張って出塁した“ボコ”【シーズン記録】
シーズン最多死球記録は、2007年にオリックス・バファローズに在籍していたグレッグ・ラロッカ選手の28個です。
ラロッカ選手は、際どいボールに対しても体を引かないファイティングスピリットあふれるプレースタイルで知られ、広島東洋カープ時代の2004年にも23死球を記録しています。
1952年に岩本義行選手が記録した24個を55年ぶりに更新した際には、怒る素振りも見せず、むしろ記録達成を喜ぶ姿を見せファンから拍手を送られました。
| 順位 | 選手名 | 所属球団 | 死球数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレッグ・ラロッカ | オリックス・バファローズ | 28 | 2007年 |
| 2 | 岩本 義行 | 大洋ホエールズ | 24 | 1952年 |
| 3 | グレッグ・ラロッカ | 広島東洋カープ | 23 | 2004年 |
| 3 | アーロン・ガイエル | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | 2007年 |
| 5 | 城島 健司 | 福岡ダイエーホークス | 22 | 2004年 |
知っておくと便利な四球と死球の豆知識

四球と死球には、基本的なルールや記録上の扱いの違い以外にも、知っておくと野球観戦がさらに面白くなる豆知識が存在します。ここでは、審判のジェスチャーの違いや、試合の勝敗を分けることもある「押し出し」について掘り下げて解説します。
審判のジェスチャーの違い
球審が四球や死球を宣告する際のジェスチャーには、明確な違いがあります。一見似ている状況ですが、審判の動きに注目することで、何が起こったのかを瞬時に理解できます。
| 種類 | 主なジェスチャー | 状況 |
|---|---|---|
| 四球 (フォアボール) | 球審は「ボール、フォー」と宣告し、打者に対して左手で一塁を指し示す動作をすることが一般的。 プレーは継続しているため、捕手がボールを逸らした場合(パスボール)や投球が大きく逸れた場合(ワイルドピッチ)、走者は次の塁へ進塁を試みることができる。 | ボールインプレイ (プレー継続) |
| 死球 (デッドボール) | 球審はまず両手を大きく広げて「タイム」を宣告し、プレーを中断させる。 その後、「ヒット・バイ・ピッチ」と告げ、打者に一塁へ進むよう指示する。 | ボールデッド (プレー中断) |
四球(フォアボール)の場合、プレーは継続中(ボールインプレイ)ですが、死球(デッドボール)の場合はプレーが一時中断(ボールデッド)するというルール上の違いが、ジェスチャーにも表れています。
押し出しが発生する条件
「押し出し」とは、満塁(すべての塁に走者がいる状態)の場面で、打者が四球または死球によって一塁へ進むことを余儀なくされた結果、他の走者も次の塁へ進塁せざるを得なくなり、三塁走者がホームインして得点が入ることを指します。 劇的なサヨナラ勝ちにつながることもある、野球の醍醐味です。
押し出し四球
満塁の状況で、打者が四球を選んだ場合に発生します。投手としてはストライクゾーンで勝負したい場面ですが、制球が定まらずにボールを4つ与えてしまうと、相手に得点を献上することになります。この場合、四球を選んだ打者には打点1が記録されます。
押し出し死球
押し出し四球と同様に、満塁の状況で打者に投球が当たってしまった(死球)場合に発生します。打者は一塁へ進み、すべての走者が1つずつ進塁するため、三塁走者がホームインし得点となります。こちらも、死球を受けた打者に打点1が記録されます。 投手にとっては、最も避けたい失点の1つと言えるでしょう。
まとめ

本記事では、四球と死球の違いをルールと記録の面から解説しました。四球は投球が4つボールになること、死球は投球が打者に当たることで、どちらも打者は一塁へ進みます。しかし、故意四球や危険球といったルールの有無、満塁時の打点の付き方など、記録上の扱いに明確な違いがあります。これらの違いを理解すれば、試合の状況判断や選手の成績への影響がわかり、野球観戦がより一層深まるでしょう。